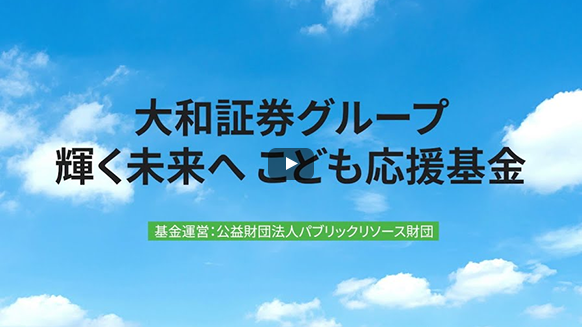NPO法人フェアスタートサポート

児童養護施設を対象とした
地域密着型就労支援の事業開発
助成金額:9,700,000円(3年累計)
実施期間:2020年1月~2022年12月
永岡 鉄平(代表理事)
団体概要
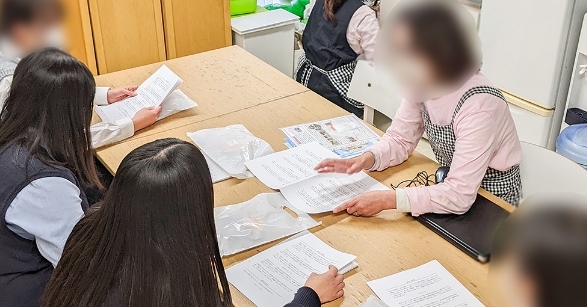
私たちフェアスタートでは、さまざまな事情で家族と暮らせず、児童養護施設をはじめ社会的養護のもとで成長した若者たちへの就労支援を行っています。
児童養護施設出身の若者たちは、多くの場合18歳程度で社会に出なくてはならなくなります。しかし、不安があっても相談できる相手がなかなかおらず、金銭的なサポートも得られない中、自立して生きていくことはそう簡単ではありません。
特に、自分がどんな仕事をしたいのかもわからず、何の準備もしないまま社会に飛び込んでしまうと、うまく環境になじめずに早々にレールを下りてしまうことになりがちです。児童養護施設を出て就職した若者の場合、働き始めて1年未満のうちに約半数が辞めてしまうというデータもあります。十分な収入を得られず、生活が困窮してしまうケースも少なくありません。
そうならないよう、本人が自分の知識や経験、関心にあわせた進路を選べるよう、会社見学やインターンシップの機会を提供するとともに、施設と企業、双方のニーズに耳を傾け、つなぐコーディネーターとしての役割を担っています。あわせて、こうした問題についての情報発信にも力を入れています。

今回の事業開発で行ったこと
今回の事業では「就労支援」をキーワードにした、児童養護施設と地域企業との関係性の構築に取り組みました。以前からずっと行ってきた取り組みではあるのですが、今回の事業で特にこだわったのは「地域密着」です。
これまでの就労支援では、施設と企業との距離感についてはそれほど意識してきませんでした。しかし、物理的な距離も近い施設と企業とをつなぐことで、直接のコミュニケーションが容易になり、若者たちの状況についての情報共有もしやすくなるのではないか。そう考え、「思い立ったらすぐ訪ねられる」程度の距離感でのマッチングができるよう、地域で協力企業を開拓していきました。

3年間の取り組みで行ったこと
初めの1年間は、企業と施設双方に、児童養護施設で育った子どもたちへの就労支援、キャリア教育などの意義について丁寧に説明するところから始めました。
また、企業と施設職員、さらには企業と施設の子どもたちの交流会などコミュニケーションを取れる場を設定。信頼関係の構築に努めました。
2年目からは、当初のねらいどおり施設と企業が直接コミュニケーションを取る事例も出てきました。また、若者たちを対象にした企業見学会や、地元企業によるキャリア授業を実施。そこから、実際に就職に至ったケースもありました。

達成できたこと、できなかったこと/子どもの貧困解決に対してどういったインパクトを生んだか

今回の事業では、参加した8施設に対し、計118社の企業を開拓することができました。交流会は計19回、会社見学や就労体験は48回実施。実際に就職につなげることができたケースは、アルバイト雇用が5件、正規雇用が5件(うち2人は2023年度入社内定)でした。交流会や企業見学会自体も、施設の若者たちにとっては「知らなかった仕事について知ることができた」「いい大人に出会えた」という貴重な機会になったと考えています。
施設と企業のつながりができた後、施設の職員が「この子にはこの会社が合うんじゃないか」と考えて推薦し、それで実際に結果が出たこともあります。人と人をつなぐことで化学反応が起こり、想定していた以上の結果が生まれるということを改めて実感しました。
私たちの就労支援によって仕事に就いた若者たちは、児童養護施設出身の若者たち全体と比較して、非常に定着率がいいのですが、その背景には、施設と企業がさまざまなことを相談し合える関係性を構築しているということがあると思います。受け入れる若者の性格や特性、配慮すべきことなどの情報を施設と企業とが共有し、採用が決まった後も施設がしっかりとフォローしていく、そういう体制を作り上げられているのです。
これまで、地元の企業と施設との関係性は、寄付をする、もらうというものにとどまっていました。今回の事業を通じて、施設が地元企業を「いろいろなことを相談できる相手」と認識できたことは、子どもたちにも非常に有益な変化といえるのではないでしょうか。施設の方も、その関係性を非常に楽しんでくださっていると感じています。
今後の取り組みと展望/資金提供者となりうる民間企業へのメッセージ
今回の事業でやったように、まずは我々が施設と企業の接点を作り、2年目くらいからは直接コミュニケーションが取れるよう、交流会や見学会を通じて関係性をどう深めていくかといったノウハウを伝えてバックアップしていく。この3年程度のサイクルを一つのパッケージとして、神奈川県だけではなく全国に広めていくことが今後の課題です。そのための素地は今回の事業でできたと考えており、広島や大阪、青森など、各地で少しずつ取り組みが始まっています。
コロナ禍においては、感染防止のため会社見学会や交流会を延期・中止しなくてはならなかったりと難しい部分も多くありました。一方で、オンラインでのコミュニケーションが充実したことで、こうした地方での取り組みも、ずっと現地に張り付くのではなくオンラインで連絡を取り、遠隔で進めていけるようになったことは収穫だったと考えています。さらに一歩進めて、関わってくださる企業から寄付もしくは会費をいただき、今後の活動に生かしていけるような仕組みづくりも視野に入れています。
また、児童養護施設の中には、就労支援にまだ前向きではないところがあるのも事実です。人手も十分ではない中、日々の子どもたちの生活を支えることに必死で、その先を考える余裕がないのだと思います。
だからまずは、それでも子どもたちのために「なんとか取り組みたい」と考えてくれる施設と協力して、先行事例をしっかり作っていきたい。さらにその事例について、私たち自身が発信していくだけではなく、施設の職員自身が同業者に対して発信していってくれれば、就労支援の重要性が伝わっていくのではないでしょうか。そのためにも、この10年は企業と施設をつなぐこととともに、職員さん達の就労支援の士気をこれまで以上に高めていくことに尽力していこうと考えています。

私たちが取り組んでいる、社会的養護で育った若者たちへの就労支援は、ただ「放っておくと貧困に陥るかもしれないかわいそうな若者を支援する」というだけの活動ではありません。少子高齢化が進む日本では今後、労働人口がどんどん減少していくのは確実です。その中では、若者たち一人ひとりが適材適所、自分を活かせる仕事を得て活躍できるようになっていかないと、国全体が立ちゆかなくなるのではないでしょうか。
しかし、現在の国の政策において、若者への就労支援、とりわけ社会的養護で育った若者への就労支援に十分な予算が取られているとはいえません。その状況では、我々のような民間団体がまずは切り込み、新しい支援の形を生み出していく、そこから国としての仕組み作りへとつなげていくことが重要だと考えます。ただ、昨今のSDGs等の流れもあり、国に頼ることなく、各地の企業が自分達の地域の子どもたちを自分事として支えていく文化が出来るとしたら、それはそれで素敵なことだと思います。そこも実は目指したいですね。多くの企業は、こうした課題を知らないだけ、実はとても興味があるのに、という事が多くあると思います。日本の企業が持つポテンシャルを私は強く感じています。
そのためにはやはり資金的な支援が絶対に必要です。ぜひ、多くの方にこの問題を知っていただき、ご支援をいただければと思います。